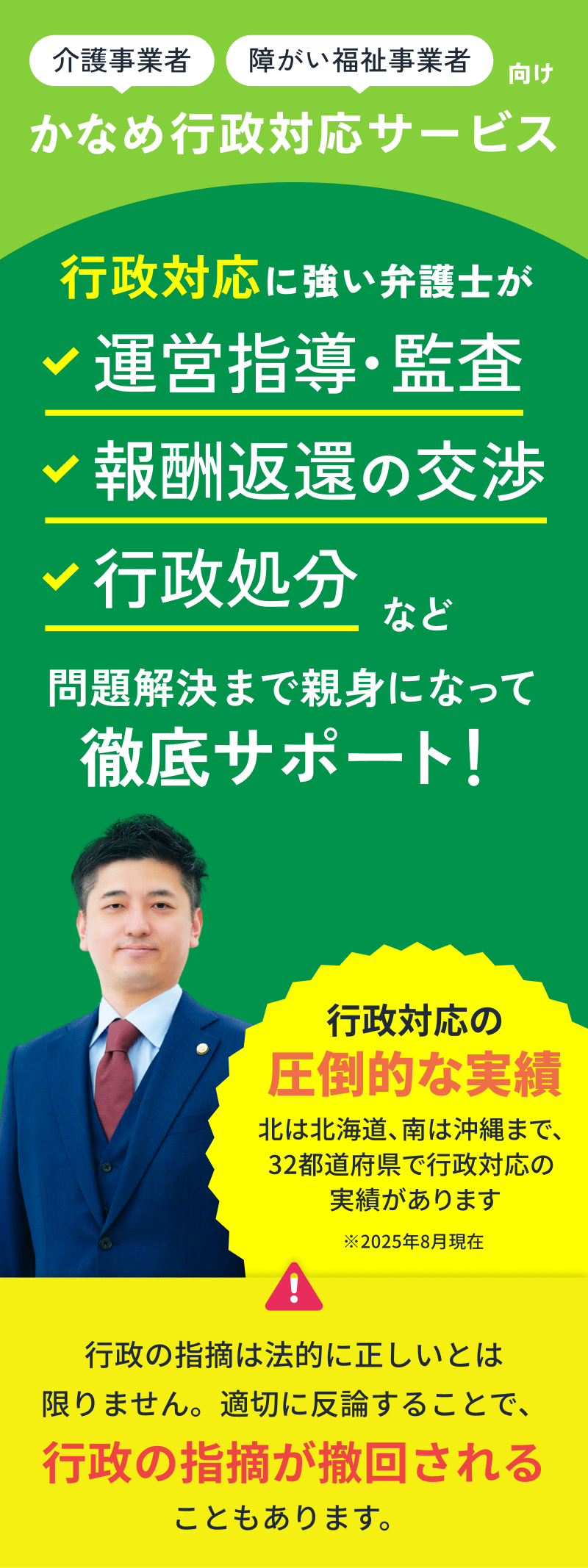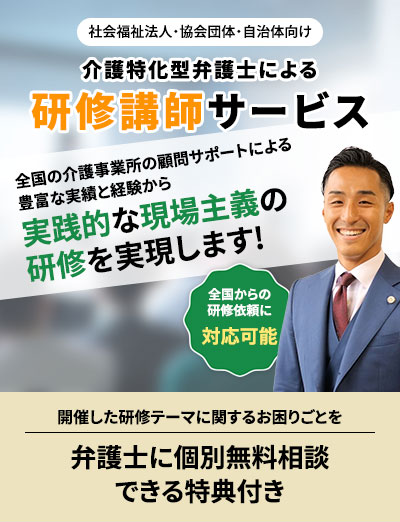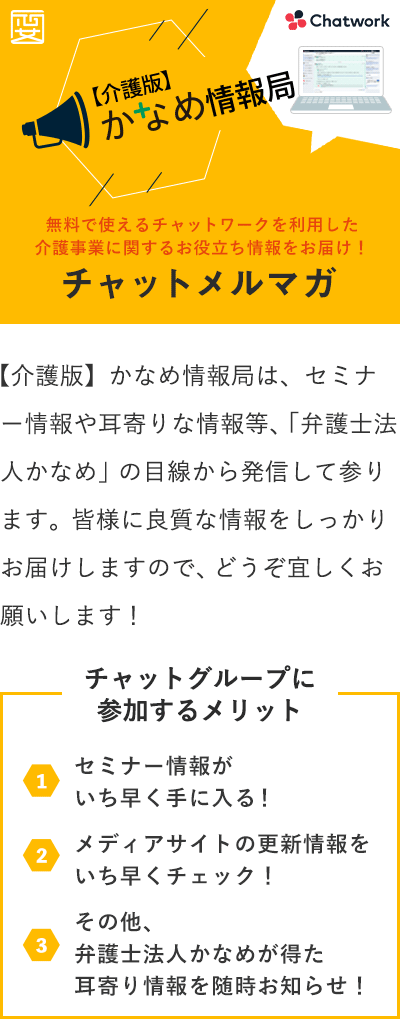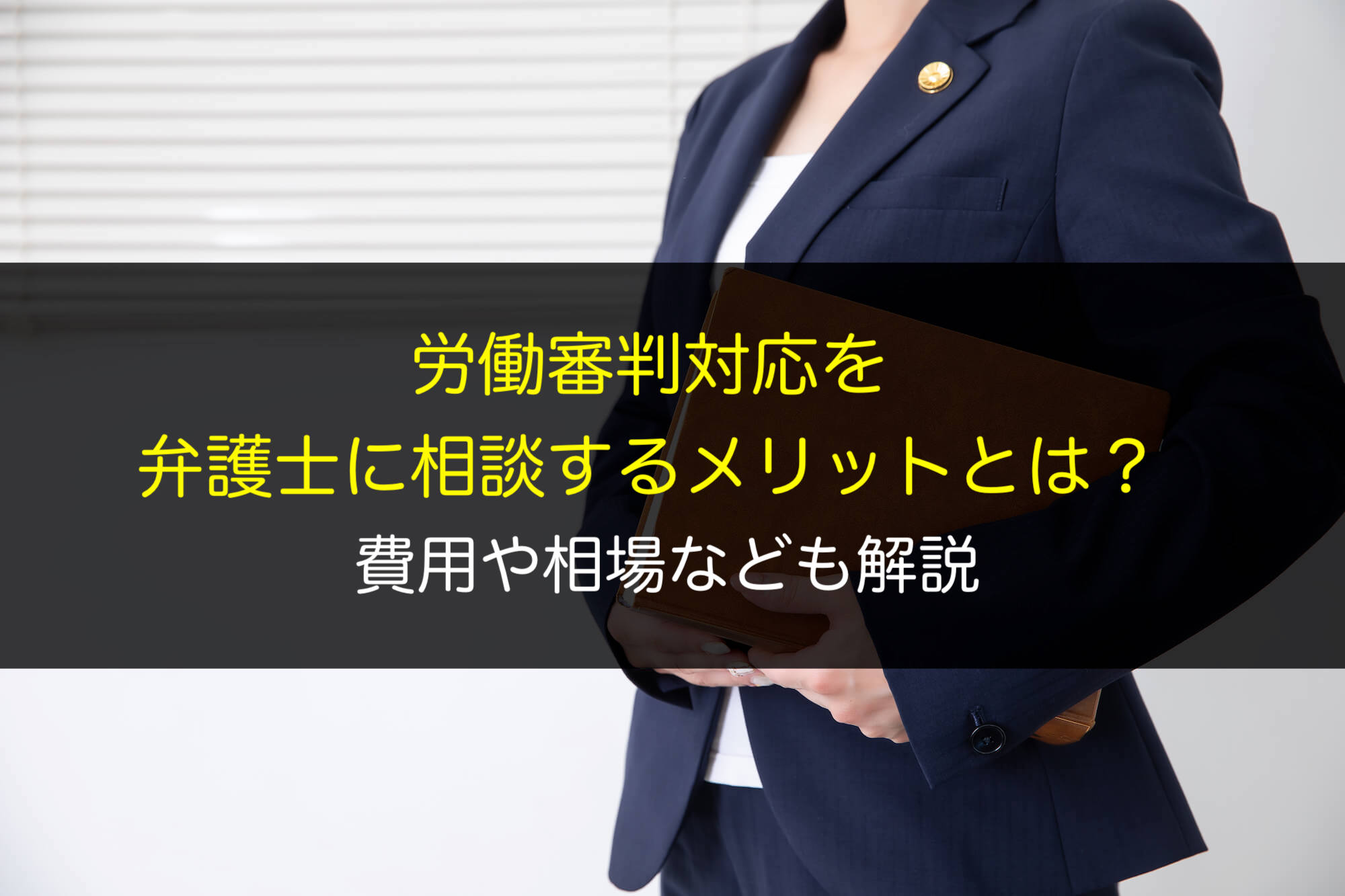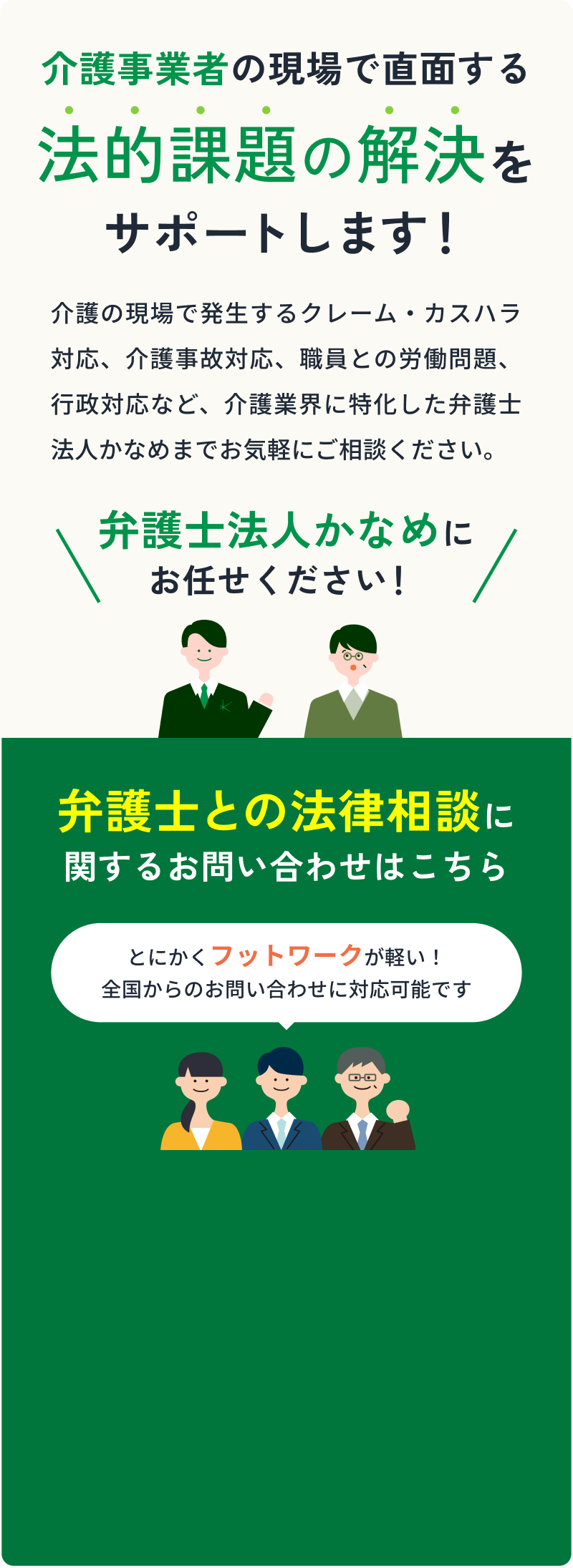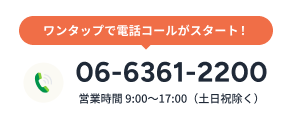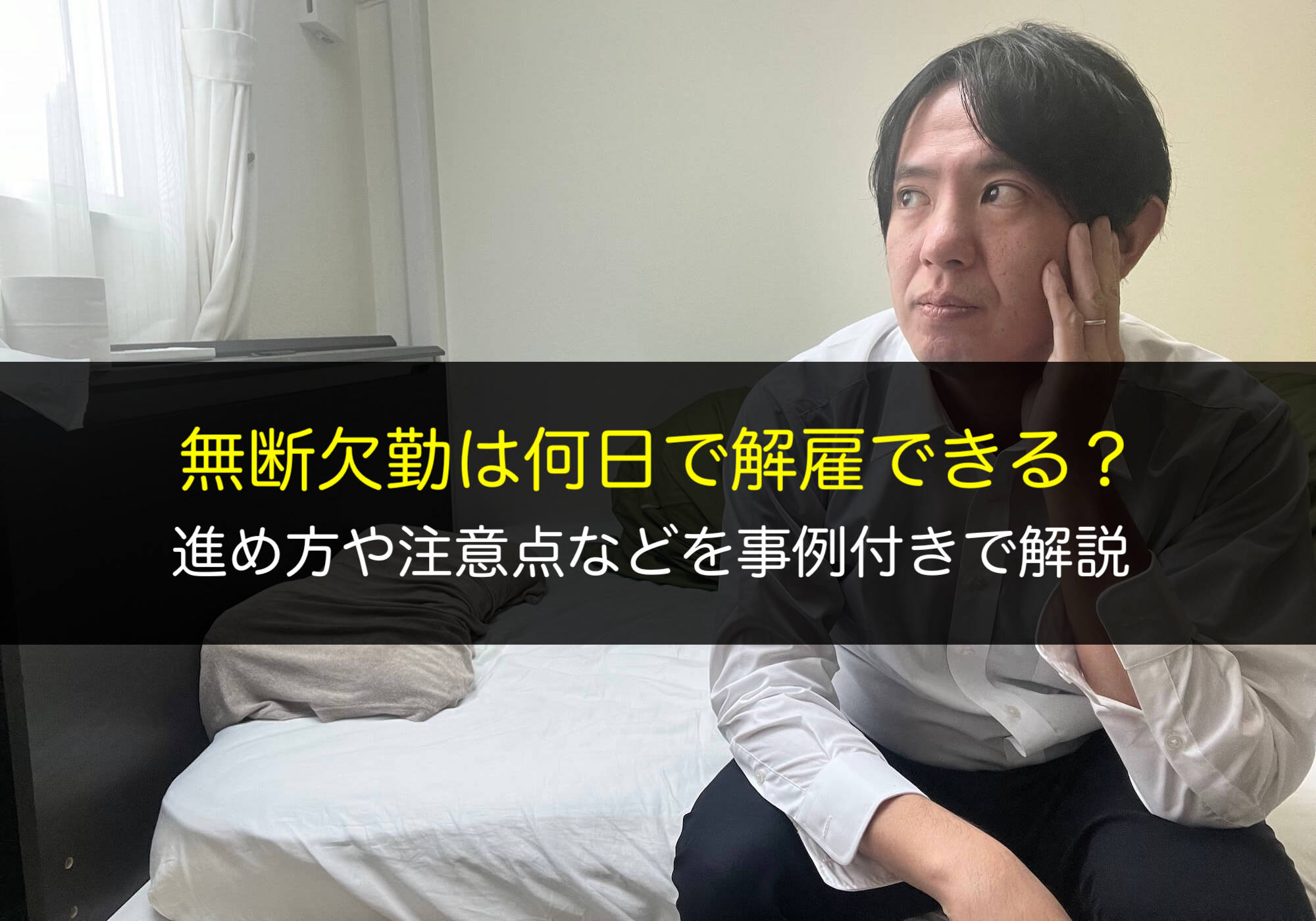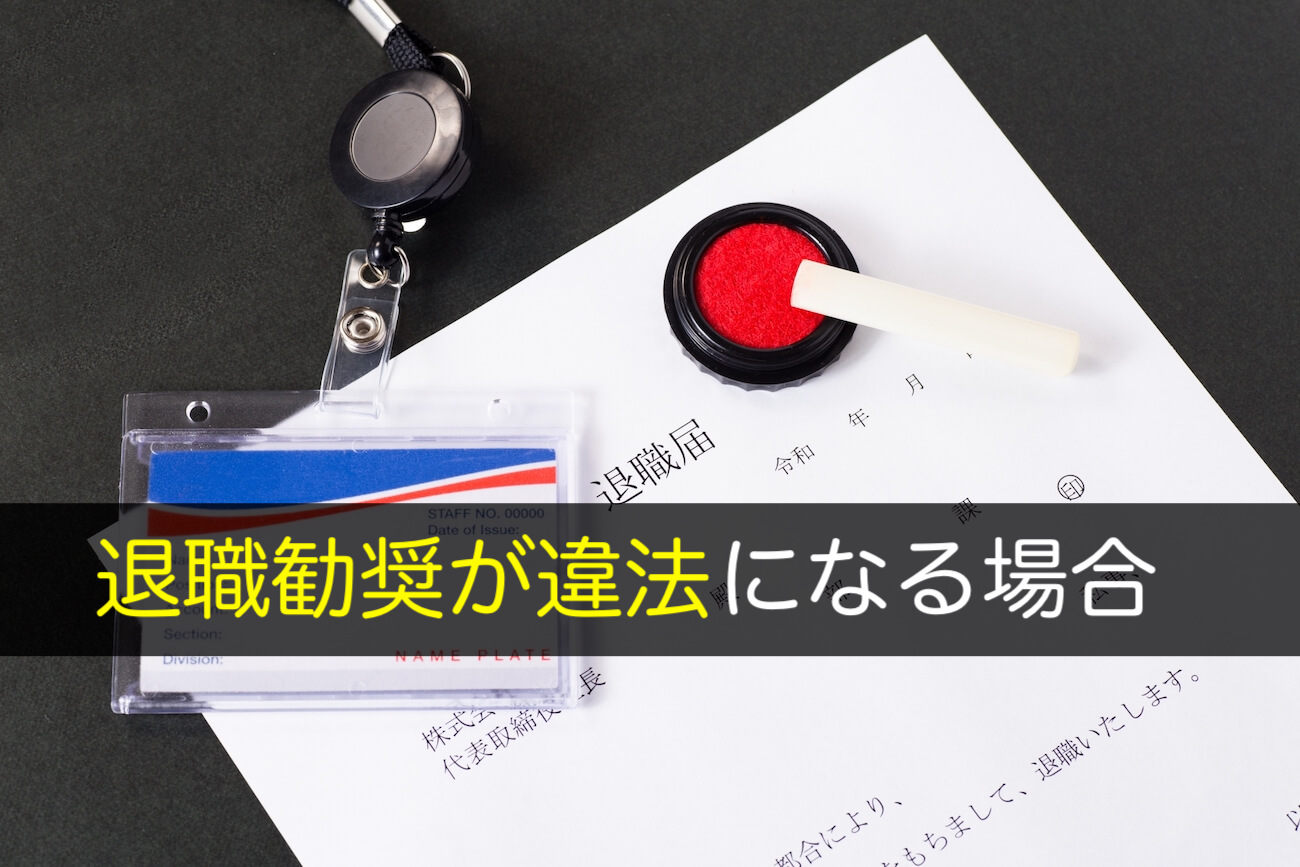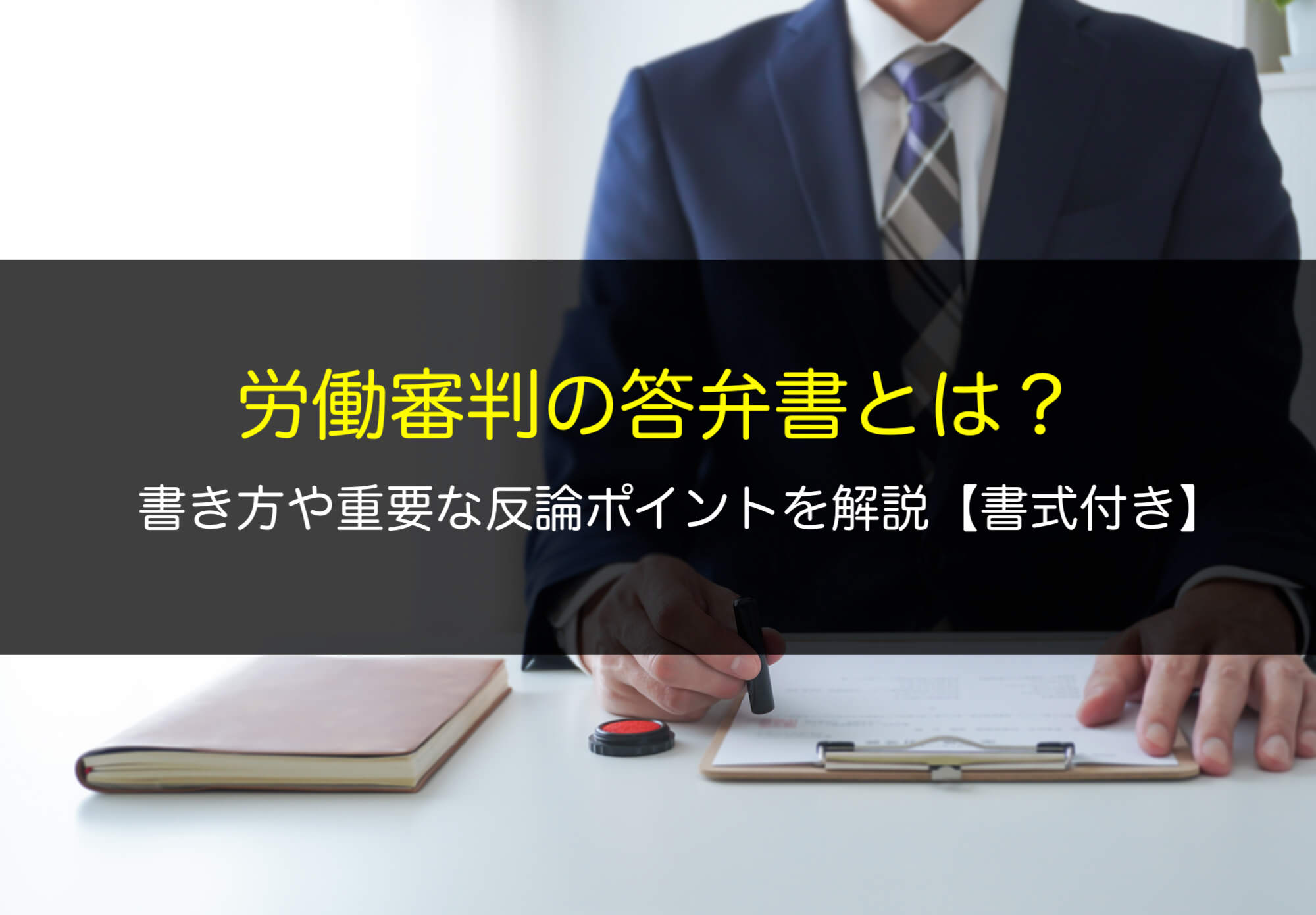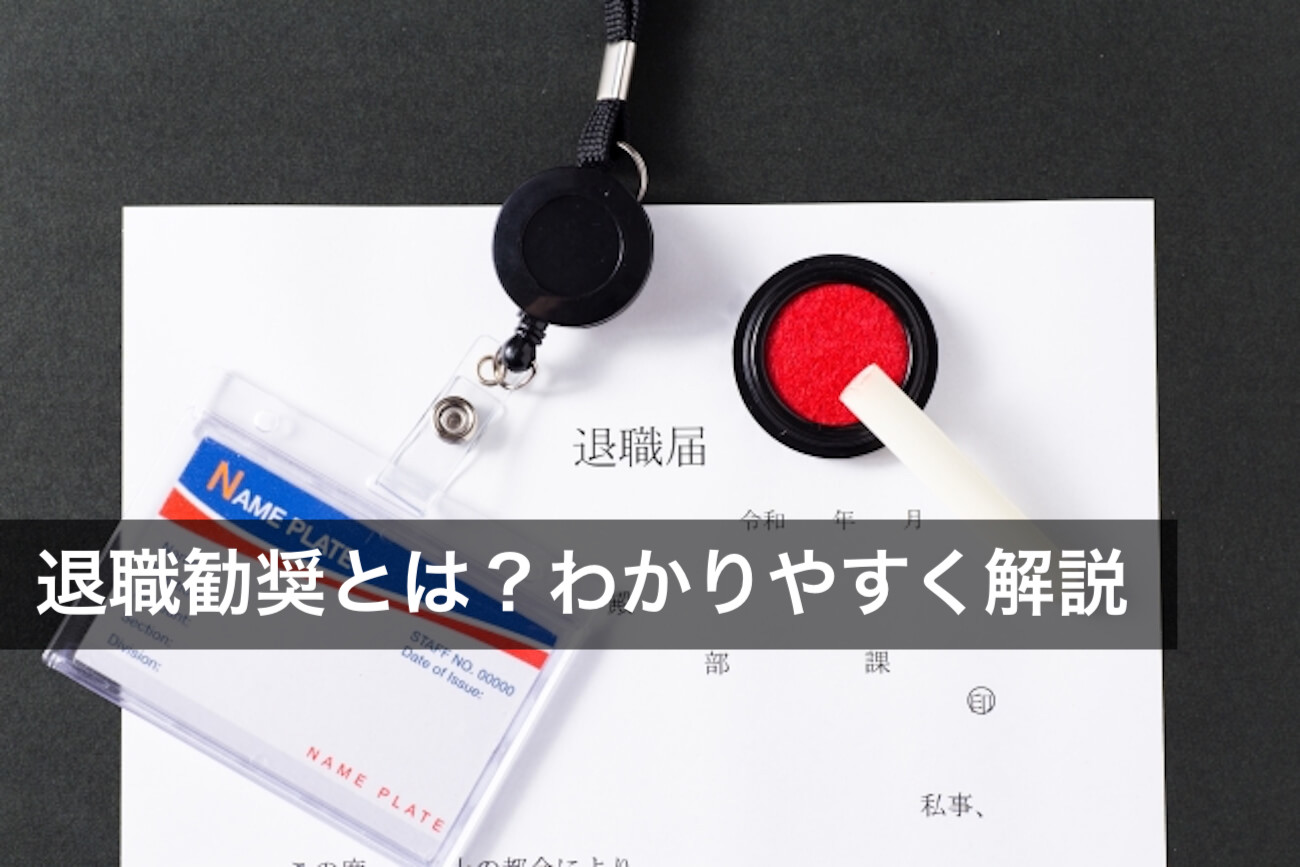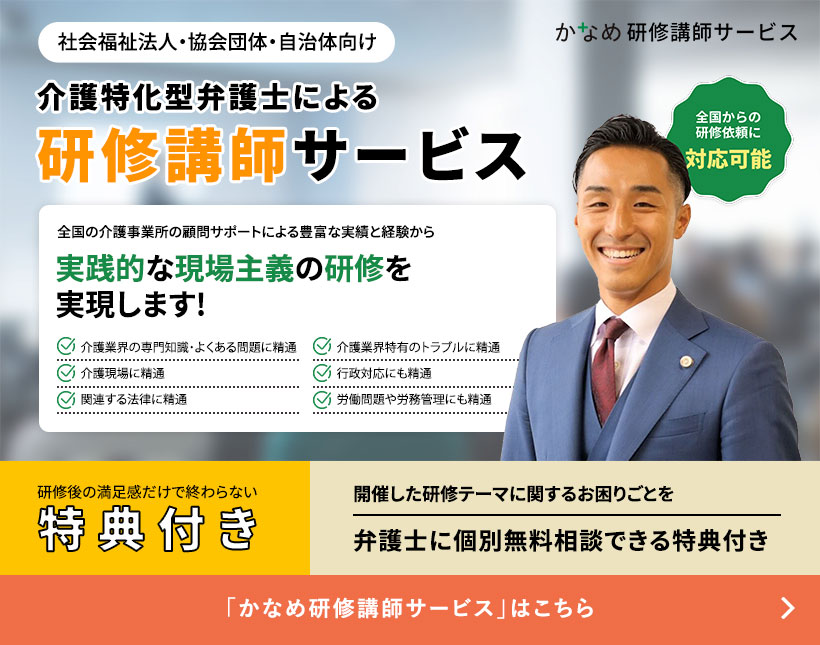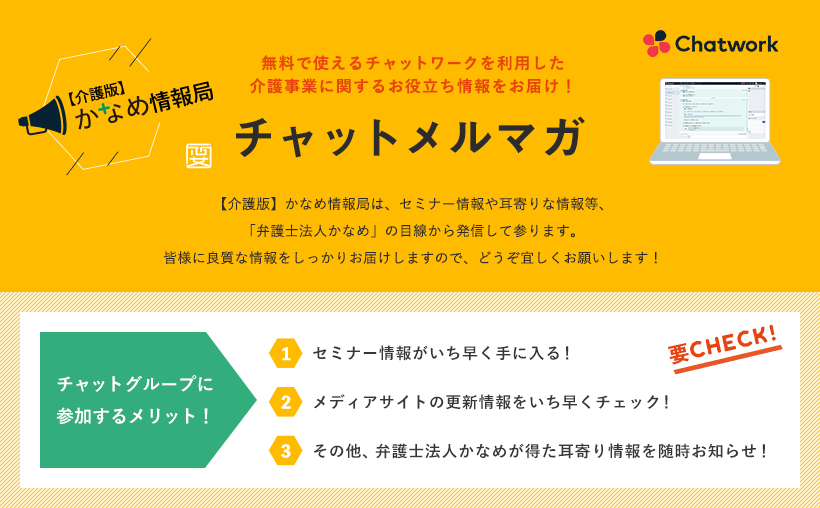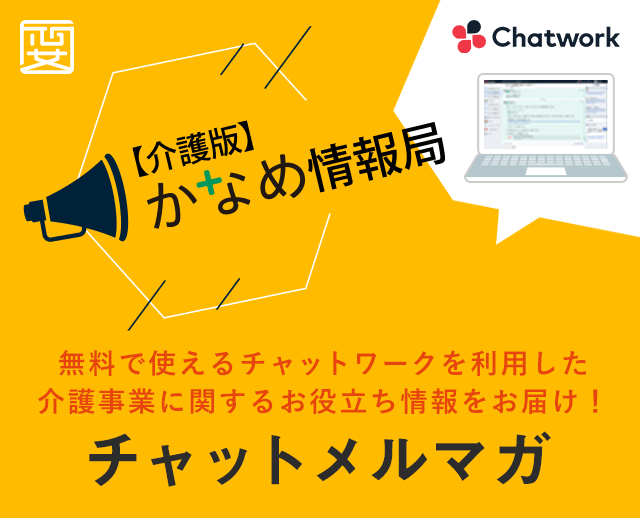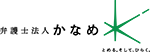ある日突然裁判所から事業所宛に郵便が届き、驚いて中身を見てみると「労働審判手続申立書」と書かれた書面で、退職した職員の名前が書かれていた…。
このような事態になった場合どのように対応すれば良いのか、すぐに判断できる事業所の方は少ないのではないでしょうか。
労働審判とは、労働者と雇用主との間で発生した労働関係のトラブルを解決するための制度です。「労働審判手続申立書」が届いたということは、労働者から事業所に対するなんらかの責任に基づく損害賠償等の請求が申し立てられたということです。
労働審判対応は、その手続きの性質上、早期に適切な手続きを進めていくことが非常に重要であり、法的な専門知識も必要であるため、申立書が届いたらすぐに弁護士に相談すべきです。
しかし、弁護士に依頼するとなると、具体的にどのような対応をしてくれるのか、費用はどれくらいかかるのか、どうやって依頼する弁護士を探せば良いのか等、分からないことも多いかと思います。
実は、労働審判の場合、申立てをする「労働者側」と申立ての相手方となる「事業主側」とでは対応の仕方が異なります。「事業主側」の対応は、時間との戦いになる面もある上、労働法は基本的に労働者側に有利な内容であるため、労働問題を専門としていない弁護士では対応が難しい場合があります。
したがって、労働審判を有利に進めるためには、労働問題に精通した経験豊富な弁護士に依頼する必要があるため、弁護士の選び方も非常に重要になります。
そこで、この記事では、労働審判対応を弁護士に相談するメリットや弁護士費用、労働審判に強い弁護士の探し方について、具体的な事例を挙げながら解説します。労働審判対応における弁護士と依頼者の関わり方や弁護士の役割を、弁護士法人かなめが実際に経験した事例をもとに解説していますので、最後まで読んでいただくと、労働審判対応を弁護士に依頼した場合の具体的なイメージが持てるかと思います。
ぜひ最後までご一読ください。
この記事の目次
1.そもそも、労働審判について
労働審判は、労働者と事業主の間で発生する労働関係のトラブルを、迅速、適正かつ実効的に解決するための手続きです。労働審判は、原則3回以内の期日で終結し、その中で話合いによる解決(調停)を図るので、早期の紛争解決が期待できることが特徴です。
一般的に労働審判でよく争われているトラブルとしては、解雇・雇止め・残業代の請求等があります。事案の性質として、早期の金銭的解決になじむものが労働審判で争われることが多いです。
2.労働審判対応を弁護士に依頼するメリット
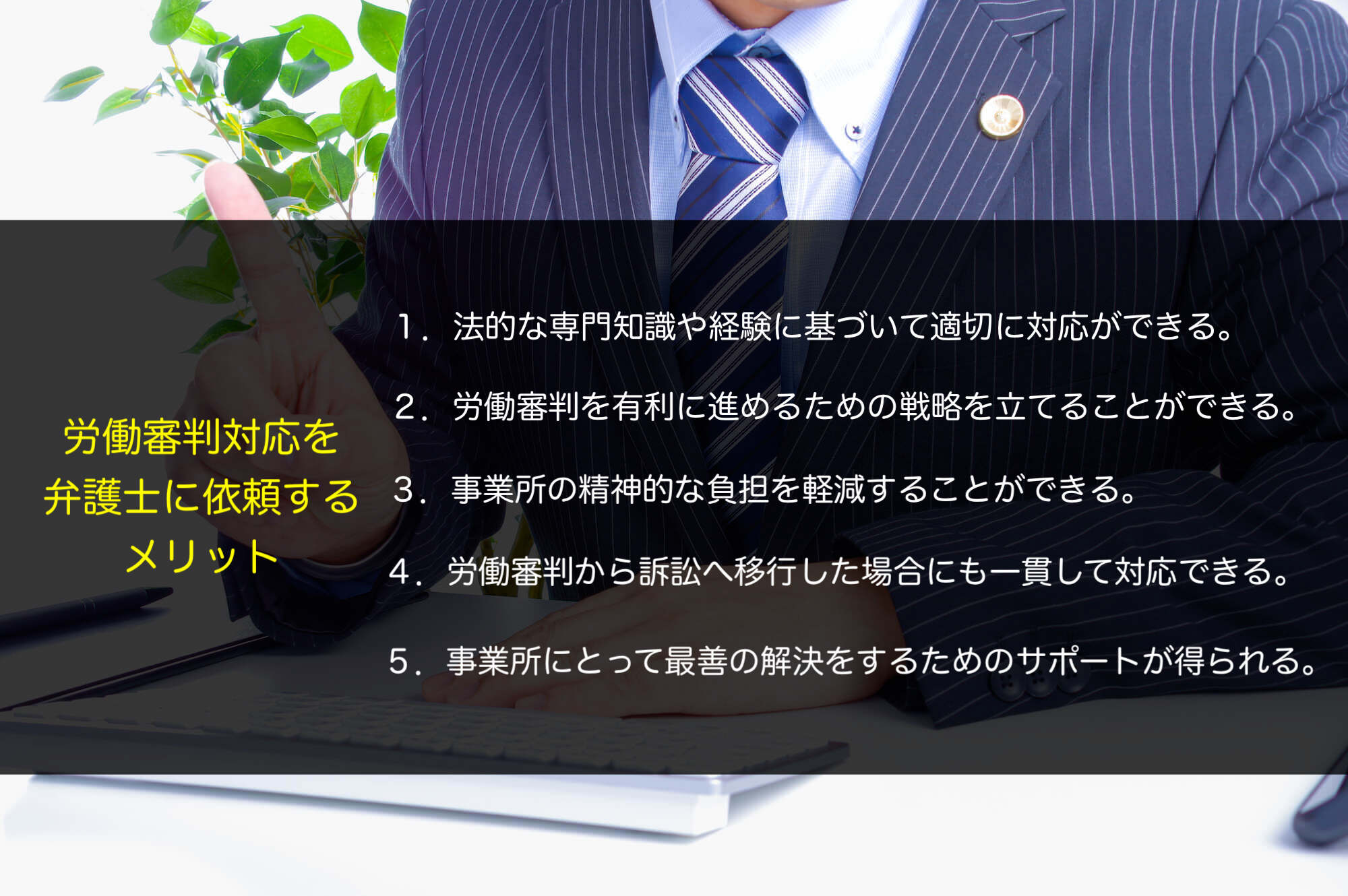
労働審判対応を弁護士に依頼した場合、以下のようなメリットがあります。
- 法的な専門知識や経験に基づいて適切に対応ができる。
- 労働審判を有利に進めるための戦略を立てることができる。
- 事業所の精神的な負担を軽減することができる。
- 労働審判から訴訟へ移行した場合にも一貫して対応できる。
- 事業所にとって最善の解決をするためのサポートが得られる。
これらのメリットについてそれぞれ詳しく解説します。
2−1.専門知識と経験
労働審判手続きには以下のような専門知識や経験が求められます。
(1)労働審判制度に関する知識
労働審判は、通常の裁判と異なり早期の紛争解決を目的とするため、手続きの流れや戦略の立て方には独特のポイントがあり、労働審判制度自体に関する知識が必要となります。
(2)労働関係法令の知識
労働審判には、労働審判法や労働審判規則等の法律、労働関係法令である労働基準法・労働契約法・労働関係調整法・民法等、様々な労働関係の法律が関係してきます。したがって、労働審判に対応するためには、各トラブルに関わる労働関係の法律の知識が不可欠です。
(3)答弁書の作成と証拠書類の収集
労働審判では、事業主側は、「申立書」の送付を受けた後、約1ヶ月以内に、「答弁書」を裁判所に提出する必要があります。答弁書とは、労働者側の主張に対する事業主側の主張・反論をまとめた書面です。答弁書の作成には、法律の専門知識が求められることはもちろん、事案に関する法的論点を分かりやすくまとめる技術が必要になります。
また、答弁書には争点となる事実を裏付けるための証拠書類の添付が求められます。証拠書類も、事案によって必要な資料が異なるので、適切な資料の収集には手続きに関する専門的な知識が必要になります。
▶参考:答弁書の重要性や記載する内容などについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。
以上のように、労働審判対応には様々な法的な専門知識や経験が求められますので、弁護士に依頼するとこれらの知識・経験に基づいて適切に手続きに対応することができます。
2−2.労働審判を有利に進めるための戦略
労働審判は、事案によっては事業主側に不利な状況で始まることも少なくありません。
一例をあげると、辞めた職員から残業代請求が申し立てられた事案で、タイムカード等で労働者の勤怠管理をできておらず、労働時間を正確に把握できていないようなケースでは、事業主側に対する労働審判委員会(労働審判手続きを取り仕切る3名の合議体のこと)の心証が悪くなってしまうという点で、事業主側にとっては不利な状況であるといえます。
そのような場合でも、労働問題に精通した弁護士であれば、例えば、あらかじめ譲歩できるラインを設定した上で解決金での和解を提案し、調停(合意)での解決を目指している労働審判委員会の心証を良くして、手続きを有利に進める、といった戦略を立てることができます。
このように、事案に応じて、事業主側が有利になるよう戦略的に手続きに対応できることは、労働審判を弁護士に依頼する大きなメリットです。
2−3.精神的な負担軽減
労働審判手続きに伴う答弁書の作成や証拠書類の収集、期日への出頭は、法的な専門知識や裁判経験のない一般の方にとっては非常に負担の大きいものです。
弁護士に労働審判対応を依頼すると、答弁書等の書面の作成は弁護士に任せられますし、証拠の収集にあたっての的確なアドバイスも受けることができます。期日にも弁護士とともに出廷でき、交渉も弁護士が行いますので、精神的な負担はかなり軽減されるでしょう。
2−4.訴訟への移行にも対応
労働審判で調停が成立しなかった場合、それまでの当事者の主張や提出された書面をもとに、労働審判委員会による審判が行われます。さらに、審判に対して不服がある場合は、異議申立てをすることができ、そのまま訴訟手続きに移行することとなります。このように、労働審判が訴訟の手続きに移行したときにも、一貫して弁護士が対応することができます。
2−5.事業所にとって最善の解決をサポート
労働審判は、事実関係について相手方と徹底的に争うというよりも、話合いでお互いの落としどころを見出しながら和解による早期解決を図る、という性質が強い手続きとなります。
労働審判で調停が成立せず訴訟移行した場合、お互いに譲歩の余地が少なくなってしまい、解決に時間を要する可能性が高くなる上に、訴訟で改めて主張立証をしたとしても、裁判官の心証が変わらないことも多く、そうすると時間や費用を無駄に費やしてしまうことになりかねません。したがって、事業所としては労働者に対して言い分があったとしても、場合によってはある程度譲歩して早期解決を図る方が、結果として事業所の損害が少なく済む場合もあります。
労働紛争の解決実績が豊富な弁護士であれば、個々の事案に応じてどのような解決方法が事業所にとって最善であるかを見極めてアドバイスすることができます。
【弁護士畑山浩俊のワンポイントアドバイス】
弁護士の他に、労働分野の専門家として、社会保険労務士があげられます。社労士は労働問題や社会保険の専門家として、事業所とも繋がりがあることが多いかと思います。
では、労働審判対応は弁護士と社労士ではどちらに相談するのが良いのでしょうか。弁護士と社労士の大きな違いは、労働審判手続の代理人となれるかどうかという点です。
労働審判は、裁判所で行われる民事紛争解決の手続きであるため、原則として弁護士しか代理人になることはできません。したがって、労働審判の答弁書を作成したり、期日に出頭して交渉を行うことは、法律上、弁護士にしかできません。
一方で社労士は、労務管理の専門家であり、事業所の顧問社労士であれば当該事業所の就業規則、給与規定や人事規程等については弁護士よりも詳しい場合もありますので、会社の実情に基づいたアドバイスを受けられることがあります。
ただし、社労士は労働審判手続き自体に代理人として関与することはできませんので、労働審判対応を全面的にサポートしてもらいたい場合は弁護士に依頼する必要があります。
各事案の状況と事業所のニーズに合わせて、弁護士と社労士どちらに相談するのが良いか判断するようにしましょう。
3.労働審判対応における弁護士の役割
労働審判対応における弁護士の役割としては、以下のようなものが挙げられます。
- 事業主側の主張や反論についての方針決定
- 答弁書の作成
- 証拠の収集
- 期日への出頭
- 手続き全体を通しての助言、サポート
ここでは、労働審判対応を弁護士に依頼した場合にどのようなサポートを受けられるのか、具体的な事例をもとに解説します。
3−1.事例
特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人(以下、Y法人という)に、ある日、裁判所から「労働審判申立書」が届いた。
労働審判申立書は、つい1ヶ月ほど前に、勤務態度が不良であることを理由に注意指導した後に退職をした職員(以下、X職員という)が申し立てたもののようで、内容を見ると未払いの残業代を支払え、という内容であった。さらに、裁判所からの書面には「呼出状」というものも入っており、労働審判の日は3週間後、「答弁書」の提出期限は2週間後とされていた。
3−2.弁護士への相談
(1)チャットワークでの第1報
労働審判申立書の送付を受けて、Y法人の代表者であるA(以下、代表者Aという)は、以前から顧問契約を締結していた法律事務所Kに対して、チャットワークというツールを利用し、対応をお願いしたい旨をチャットで伝えた。するとH弁護士からすぐに回答があり、労働審判手続きは時間との勝負であるため、今後の進め方について早急に方針を決定し、答弁書の作成に着手する必要がある旨を告げられた。そして、以下の資料データを送付してもらい、内容を確認した上で、今後の方針について2日後にZOOMで打ち合わせを行うこととなった。
- 労働審判申立書
- 雇用契約書
- タイムカード等のX職員の勤務時間が分かる資料
- 業務日報
- 退職届
- 就業規則
- 人事記録(注意指導を行った記録のあるもの)
(2)方針の決定
相談から2日後の打ち合わせは、代表者Aと、X職員が勤務していた老人ホームの所長であるB(以下B所長という)とH弁護士で行われた。
・H弁護士:これから今後の方針等を決めていきたいと思いますが、まず初めに今回申立てられた「労働審判」についてご説明させてください。
通常の裁判は、かなり長い時間をかけてお互いに事実関係について主張・立証した上で、裁判官の判決をもらうというものですが、労働審判は早期の実行的な解決を目的としている手続きであるため、期日の回数が原則3回と決まっており、その中で調停と呼ばれる合意による解決を図ることが大きな特徴です。
しかも基本的には1回目の期日でお互いの主張・立証を尽くす必要がありますので、第1回期日までの準備が非常に重要なポイントとなります。今回申立書と共に届いている「第1回労働審判手続期日呼出状及び答弁書催告状」によると、「答弁書」の提出期限が今から2週間後の〇月〇日になっていますので、それまでに答弁書を作成して、証拠になる書類もそろえなければなりません。つまり、非常にタイトなスケジュールで進めていく必要があることをご理解いただきたいです。
・代表者A:分かりました。こちらもすぐに対応できるように準備しておきます。
・H弁護士:ありがとうございます。答弁書の作成は当職で行いますので、事業所の方では証拠書類の収集をお願いします。
もう一つ労働審判にはポイントがあります。労働審判は基本的に「調停」での合意を図る運用がされています。つまり、お互いに譲歩できるところは譲歩して、和解による解決を目指すということです。
もちろん御所にもX職員に対する言い分はあるかと思いますが、X職員の主張に対して徹底的に争うとなると、いたずらに紛争を長引かせることになり、場合によっては時間と費用を無駄にしてしまうことにもなってしまいます。あらかじめ譲歩できるラインを設定しておいて、和解金による解決を図るという戦略が結果として損害を減らすことにもつながるということを念頭に置きながら方針を決めていきたいと思います。
・代表者A:なるほど。もちろんX職員の申立内容について反論はあるのですが、こちらとしてもあまり紛争を長引かせたいとは思っておりませんので、一定程度はこちらも譲歩しつつ早期解決することができれば良いと思っています。
・H弁護士:分かりました。では解決金の水準をどの程度にするかも含めて、これから事実関係を確認しつつ、方針を決めていきましょう。
このようにH弁護士は労働審判手続きの流れや特徴について説明した上で、代表者AとB所長に、X職員の勤務態度や退職までの経緯、事業所での注意指導の経過等の事実関係の聞き取りを行った。
・H弁護士:事実関係についてある程度把握できましたので、当職の方で早速争点となる部分をまとめつつ、答弁書の作成にとりかかります。解決金の水準の試算についても同時に進めていきますので、またご提案させていただきます。すでにタイムカード等のX職員に関する書類についてはご提供いただいていますが、追加で必要な書類等があればご連絡しますので、速やかにご提供いただきますようご協力をお願いしたいです。細かい事実関係の認否については、再度お電話等で確認させていただく必要があるかと思います。
・代表者A:ありがとうございます。書類等の収集に関してはすぐに対応できるようにしておきます。先の見通しが立って少し安心しました。引き続きよろしくお願いいたします。
3−3.弁護士による答弁書の作成・提出
1週間後、H弁護士は「答弁書」の案文を代表者Aに送付した。答弁書の内容についてH弁護士から代表者Aに電話にて説明がなされた。
H弁護士は争点となる事項について法的な解釈や判例を踏まえながら分かりやすく代表者Aに説明した。
・H弁護士:X職員は、他職員のシフトを管理する立場にあったようですが、B所長への事前確認もないまま他職員へシフト表を送ったり、自分の勤務時間が多くなるように偏ったシフトを組んだりしていたようですね。他にも業務時間内にパソコンで業務に関係のないことを検索していたり、私的な電話対応をしていたりするなどの勤務態度の不良が目立ち、B所長の指示に従わない行動が散見され、注意指導を度々行っていたということで、人事記録にも詳細に記録されていましたので、このことについても答弁書には詳しく記載しました。
・代表者A:ありがとうございます。答弁書の内容に異論はありません。X職員の勤務態度の悪さについては他職員への悪影響も懸念され、こちらとしても非常に悩まされました。B所長も粘り強く注意指導をおこなってくれていたのですが、改善されることはないままX職員から退職を申し出られました。
・H弁護士:その点についてはしっかりと期日でも主張していきたいと思います。
では、あと3日で答弁書の提出期限となりますので、答弁書の最終確認をした上で裁判所へ提出する準備を進めてまいります。
その後、H弁護士は答弁書を完成させ証拠書類と共に期限までに裁判所へ提出した。
3−4.弁護士と一緒に第1回労働審判に出廷
答弁書提出から1週間後の〇月〇日、代表者AとB所長、H弁護士は第1回労働審判期日に出廷した。出廷に先立ち、H弁護士から代表者Aに期日の流れについて説明があった。
・H弁護士:いよいよ第1回期日ですね。労働審判では、第1回期日が一番大きな山場となります。長丁場になりますが、一緒に頑張りましょう。
期日の流れを先にお伝えしておきます。まず労働審判の期日は、労働審判委員会と呼ばれる裁判官である審判官1人と労働問題に詳しい民間人である審判員2人によって進められます。審判廷にはラウンドテーブルが置かれていて、審判官と審判員を挟むような形で申立人及び申立人代理人と私たちが着席するような形になります。
最初に労働審判委員会から自己紹介があった後に「争点整理」が行われます。「争点整理」とは、今回の事案で法律上・事実上の争点を絞り込む作業です。ここで私の方から今回の争点となっている部分について、しっかりお伝えします。争点がまとまったら、「証拠調べ」に入ります。これは事実関係の確認の作業です。審判委員会から当事者に対して質問があるかと思いますが、私がきちんとフォローしますので、AさんとBさんは把握している事実について正直に答えてください。証拠調べが終わると、各当事者が別々に呼ばれて調停の打診があり、和解の調整がされます。時間として約2時間ほどの時間を要し、正念場になりますが、私がしっかり矢面に立って進めていきますので、安心してくださいね。
このように弁護士から事前に当日の流れを詳しく説明してもらったおかげで、代表者AとB所長は安心して期日に臨むことができた。
3−5.第1回労働審判を踏まえた弁護士との打合せ
・H弁護士:第1回期日、誠にお疲れ様でした。今回の期日は、次回の期日までに双方で解決金額を検討するということで終了しました。第2回、第3回の期日は、双方の意見を聞きながら和解の調整をしていく期日になります。こちらの主張としては、計算上支払うべき残業代は35万円であり、早期解決のため譲歩できるラインとしても100万円までと事前に相談していましたが、解決金の金額については異論はありませんか?
・代表者A:はい、異論はありませんが、もちろんできるだけ低い金額で解決できればと思っています。X職員にはかなり振り回されていますからね。
・H弁護士:分かりました。ではこちらの算定した未払残業代を改めてまとめた上で、次回の期日では解決金としてひとまず50万円を支払うことを提示してみましょう。
3−6.第2回労働審判への出廷
第1回期日から3週間後、代表者AとB所長、H弁護士が共に第2回労働審判期日に出廷した。
第2回期日では、双方の提示する解決金額について話合いが行われた。X職員側は200万円の解決金を求めており、双方の提示金額には開きがあったため、労働審判委員会から解決金の提案があった。認定できる労働時間については、おおむねY法人側の主張が妥当であると労働審判委員会は考えており、勤務態度に対する注意指導についても人事記録として詳細に記載されている証拠がある点が労働審判委員会の心証を良くしたようで、解決金80万円での調停が打診され、次回までに調停案を検討するということで次回持ち越しとなった。
第2回期日の所要時間は1時間程度であった。
3−7.第2回労働審判を踏まえた弁護士との打合せ
・H弁護士:書面での証拠がきちんと残っていた点で、労働審判委員会の心証がこちら側に向いているようですね。期日でも質問に対してX職員がはぐらかすような回答をしていたのに対して、AさんとBさんが審判官の質問に対して誠実に受け答えをしていた点も、良かったのだと思います。
・代表者A:ありがとうございます。先生のサポートがあったからこそです。
・H弁護士:解決金の金額としては80万円はかなり妥当な線かと思っています。相手方としても早期解決を望んでいるようですし、労働審判委員会の方針としてもX職員の主張に寄り添う方針ではなさそうなので、こちらとしては80万円の和解で調停案に応じるという方向でよろしいでしょうか。
・代表者A:はい、それでよろしくお願いします。
3−8.第3回労働審判への出廷
第2回期日からさらに三週間後、第3回期日が開催された。代表者AとH弁護士の2名で主席した。
労働審判員会から再度調停の提案があり、Y法人からX職員に解決金80万円を支払い、和解することで労働者側も合意し、調停が成立した。
3−9.和解の成立
第3回期日終了後、法律事務所Kに裁判所から調停調書の送付の連絡があった。
調停の内容としては、以下の内容であった。
- ①Y法人からX職員に解決金として80万円を支払うこと
- ②調停の内容やX職員の経緯一切について、お互いに第三者に口外しないこと
- ③今後、お互いに誹謗中傷、業務妨害、迷惑行為等を一切しないこと
- ④X職員は、その余の請求を放棄すること
- ⑤お互いに本調停内容以外に何らの債権債務がないこと
- ⑥手続費用は各自の負担とすること
H弁護士は調停内容について改めて代表者Aに連絡した。
・代表者A:無事に和解が成立してほっとしています。解決金も想定内で大きな損害にはならず、紛争がこじれることもなく終了して良かったです。H弁護士には顧問弁護士として普段から事業所の内情もよく理解していただいていたので、今回の件もすぐに相談して対応していただけて本当に助かりました。
・H弁護士:とんでもないです。Aさんがこちらのお願いにも非常に迅速に対応していただいたおかげで、スムーズに進めることができました。また何かお困り事がありましたら、いつでもご相談下さいね。
この事例をみていただいてわかるように、労働審判手続きの一連の流れの中で、弁護士は、事業主側の方針の決定、書面の作成、証拠収集、期日への出頭といった各場面で、依頼者への丁寧な説明を行いつつ、労働者側の出方に応じて臨機応変に対応するなど、非常に重要な役割を果たしています。
▶参考:労働審判の解決金については、以下の記事で金額の決まり方や相場について詳しく解説していますのでご参照ください。
4.労働審判対応を弁護士に依頼する際の費用について
労働審判の対応を弁護士に依頼した場合に必要となる費用は、主に以下の5つがあります。
- (1)相談料
- (2)着手金
- (3)報酬
- (4)実費
- (5)日当
労働審判対応において事業所側にかかる弁護士費用は、基本的に労働者側からの請求内容によって変動します。以下でそれぞれの費用について、詳しく解説します。
4−1.弁護士に支払う費用とは?
(1)相談料
相談料は、弁護士に法律相談をする場合にかかる費用です。スポットでの法律相談の際にかかることが多いです。
(2)着手金
着手金は、弁護士が事件に着手する際に必要となる費用で、事件の対応を依頼した時点で支払わなければならない費用です。その結果のいかんにかかわらず、返金されないのが原則です。
(3)報酬
報酬は、事務処理の結果に成功不成功がある事件等について、事件が解決した際にその成功の程度に応じて支払う費用です。
(4)実費
実費は、事件の手続きのために必要となる諸費用で、郵送費用、コピー代、交通費、印紙代等があります。
(5)日当
委任事務処理のために、事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されることの対価です。
4−2.労働審判対応に関する弁護士費用の相場は?
(1)相談料
相談料は、一般的には、30分5000円や、1時間1万円からが相場です。
費用の計算方法は、法律事務所によって異なりますし、法律相談の方法(対面かWEBか電話かなど)により金額に差異がある可能性もありますので、必ず確認するようにしましょう。
(2)着手金
着手金は、相手方からの請求金額や請求内容で決まります。いくらを請求されているかにより、以下のような計算がされることが一般的です。
| 経済的利益の額 | 着手金 |
| 300万円以下の場合 | 経済的利益の8% |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 | 同5% + 9万円 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 | 同3% + 69万円 |
| 3億円を超える場合 | 同2% + 369万円 |
(3)報酬
報酬金額は、弁護士が事件対応した結果得られた経済的利益から算定され、相場としては経済的利益の10%~30%となります。労働審判を申し立てられた場合の事業主側は、金銭を請求される側なので、経済的利益は、請求された金額から減額した金額が経済的利益となります。
以下のような計算をされることが一般的です。
| 経済的利益の額 | 成功報酬金 |
| 300万円以下の場合 | 同16% |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 | 同10% + 18万円 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 | 同6% + 138万円 |
| 3億円を超える場合 | 同4% +738万円 |
(4)実費
事件の手続きのために必要となる諸費用で、郵送費用、コピー代、交通費、印紙代等があります。事前に2万円ないし3万円程度を預かり金として預けることもあります。
(5)日当
日当は、移動時間及び拘束時間を基準に、以下のような定めをすることが一般的です。ただし、一律同じ金額(弁護士1人あたり5万円など)を定めることもあります。
| 往復30分まで | 5,000円 ~ 1万円 |
| 往復30分を超え2時間まで | 1万円 ~ 3万円 |
| 往復2時間を超え4時間まで | 3万円 ~ 5万円 |
| 往復4時間を超える場合 | 5万円 ~ 10万円 |
4−3.弁護士費用は相手方に請求できる?
こちらに落ち度がないのに、労働審判が申立てられたことによって弁護士費用を捻出しなければならないことになれば、弁護士費用を相手方に請求したいと考えるでしょう。しかし、弁護士費用は以下の例外を除いて、原則相手方には請求できません。
- (1)不法行為による損害賠償請求訴訟
- (2)労働災害で安全配慮義務違反を主張する場合
勝訴した当事者が敗訴した当事者に対し、訴訟費用を請求することができることを「敗訴者負担」といいます。民事訴訟法第61条には「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」と定められています。しかし、ここに記載されている「訴訟費用」には、弁護士費用は含まれません。ここにいう「訴訟費用」は、収入印紙代、郵送代、交通費等の手続きに係る費用です。
弁護士費用を敗訴者に負担させない理由としては、敗訴した場合に負担する金額があまりに過大になると、訴訟に伴う費用負担のリスクが高くなり、訴訟提起を委縮させてしまう可能性があるからです。
他方で上記の2つのケースは、一方が違法なことをして相手に損害を生じさせたという点で、被害者側はやむを得ず訴訟を起こし、弁護士に依頼して費用を支払わざるを得なくなったのだから、弁護士費用も不法行為によって被った損害に含まれる、という考え方で、加害者に弁護士費用を請求できるという判例が出ています。
したがって、労働審判における事業者側の立場としては、弁護士費用を労働者である相手方に請求することは基本的にはできないと考えておきましょう。
5.労働審判は弁護士なしでの対応が可能か?
労働審判手続き自体は、必ず代理人を立てて進めなければならないものではないため、弁護士に依頼しなくても対応することは可能です。
ただし、事業主側における労働審判手続きは、短期間での答弁書や証拠書類の提出が必要となるため、法律のプロではない事業所だけで労働審判に対応することはあまり現実的ではありません。
その上、答弁書や証拠書類の作成に不備があったり、期日でうまく主張・反論ができなかったりすると、労働者側の請求がそのまま認められてしまう可能性がありますし、紛争が長引いて訴訟に移行してしまうと、余計に費用がかかってしまう等、事業所に大きな損害を与えてしまう可能性があります。
実際に、事業主側(会社側)の場合は、ほとんどのケースで労働審判対応を弁護士に依頼しています。事業所の損害を最小限に抑えるためにも、労働審判手続きは速やかに弁護士に依頼するようにしましょう。
6.労働審判は弁護士に相談するタイミングは?
労働審判は、申立書を受け取ってから2週間~1ヶ月程で事業主側の方針の決定、答弁書の作成、証拠書類の収集などを行う必要があり、非常に迅速な対応が求められます。
弁護士への相談が遅れてしまうと、その分準備をする時間が少なくなり、適切な対応ができなくなってしまう可能性があります。申立書が事業所に届いたらできるだけ速やかに弁護士に相談するようにしましょう。
7.労働審判に強い弁護士の探し方と選び方
労働審判対応を弁護士に依頼する場合、どのように弁護士を探せば良いのでしょうか。労働審判に強い弁護士の探し方と選び方について解説します。
7−1.労働問題対応の経験と実績ある弁護士への相談が必要
お医者さんに、内科・小児科・産婦人科・泌尿器科…などの専門があるように、弁護士にも民事・刑事・債務整理・相続・労働・企業法務など、それぞれ専門の分野があるので、たとえ弁護士であっても、専門外の事案については対応が困難な場合があります。
したがって、労働審判対応の弁護士を選ぶ際には、労働問題を専門分野とした弁護士を探す必要があります。その上で、労働関係紛争を実際に対応した経験や実績のある弁護士であれば、労働審判にもスムーズに対応してもらえることが期待できます。
7−2.弁護士の探し方
では、どのようにして労働審判に強い弁護士を探せばよいのでしょうか。ここでは以下の3つの方法について解説します。
- (1)顧問弁護士への相談
- (2)インターネット検索
- (3)口コミ
以下で、それぞれの方法について解説していきます。
(1)顧問弁護士への相談
すでに顧問契約を締結している弁護士がいる場合は、まずは顧問弁護士に相談します。顧問弁護士であれば事業所の内情も把握していますし、労働問題にも詳しいと考えられますので、迅速に対応してもらうことができるでしょう。
(2)インターネット検索
弁護士を探す上で一番簡便な方法は、インターネットで検索することです。「労働審判 弁護士」等のキーワードでインターネット検索すると、労働審判についての記事を載せている法律事務所のホームページをたくさん見つけることができます。ただし、インターネット上には多数の弁護士関係のサイトがありますので、その中から最適な法律事務所を探し出す必要があります。その際、ポイントとなるのは、以下の3つです。
- 1.個人(労働者側)か法人(経営者側)どちらを対象としているか。
- 2.労働問題に精通しているか。(労働審判の経験があるか)
- 3.介護業界に精通しているか。
それぞれのポイントについて、詳しく解説していきます。
1.個人(労働者側)か法人(経営者側)どちらを対象としているか。
法律事務所の中でも、労働問題に関して、個人(労働者)を対象としている事務所と法人(経営者)を対象としている事務所があります。労働審判を申し立てられた側(経営者側)であれば、法人(経営者側)を対象としている法律事務所を選ぶ必要があります。
ホームページ上に「企業法務」「顧問弁護士」「使用者側」といったキーワードが記載されていれば「法人(経営者側)」を対象とする事務所だと考えられます。反対に「労働者側」や「解雇されたら」などのキーワードがある場合は、個人(労働者側)を対象としている事務所と考えられます。
2.労働問題に精通しているか。(労働審判の経験があるか)
法律事務所のホームページには「取扱い分野」や「実績」などが掲載されています。これらを調べてみると、どのような分野を専門としているのか、どのような紛争解決の実績があるか、労働審判対応の経験があるか等が分かりますので、労働事件関係の紛争解決の実績が豊富な法律事務所を選ぶようにしましょう。
3.介護業界に精通しているか。
業界が変われば関係する法令等も異なります。特に介護業界は介護保険法というかなり複雑な法律によって規制されていますが、介護保険法に詳しい弁護士は少なく、介護業界に精通している法律事務所は限られてきます。
労働審判における対応においても、介護業界に詳しい法律事務所であれば、より業界の労働環境等の内情を分かった上で事業主側の要求に沿った対応をしてもらえることが期待できますので、ホームページ上でその点も確認すると良いでしょう。
(3)口コミ
アナログな方法ではありますが、より信頼に足る弁護士の探し方は、口コミです。
普段から地域のコミュニティ、セミナー、研修会などでつながりのある同業者の方に、「労働問題に強い弁護士を知らないか」と聞いてみるのが良いでしょう。弁護士に依頼をした経験のある事業者、あるいは顧問弁護士と契約している事業者の方がいれば、実際の弁護士対応や費用感等も聞くことができるため、弁護士を選ぶ際の判断がしやすく、信頼できる弁護士に繋がりやすいと考えられます。
8.労働審判の対応を弁護士法人かなめの弁護士に相談したい方はこちら

弁護士法人かなめでは、労働関係紛争に精通した弁護士が以下のようなサポートを行っています。
- (1)労働審判の代理業務
- (2)介護事業者の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」
8−1.労働審判の代理業務
労働審判手続きにおける事業主側の代理人として、以下のような業務をすることができます。
- 答弁書の作成、提出
- 証拠資料の収集、精査
- 関係者への聞き取り
- 残業代等の金額の算定
- 金銭的解決を図るのであればその額の算定
- 期日への出頭
これらの他にも、事案に応じて事業主側が対応すべき手続きを代理人としてトータルに行いつつ、事業主側の対応のサポートや助言もできますので、事業主側の負担の軽減を図り、金銭的損害を最小限に抑えることができます。
8−2.介護事業者の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」
弁護士法人かなめでは、「8−1.労働審判の代理業務」サービスなど介護事業者の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」を運営しています。
具体的には、トラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入し、事業所内で何か問題が発生した場合には、速やかに弁護士へ相談できる関係性を構築しています。そして、弁護士と介護事業所の関係者様でチャットグループを作り、日々の悩み事を、法的問題かどうかを選択せずにまずはご相談頂き、これにより迅速な対応が可能となっています。直接弁護士に相談できることで、事業所内での業務効率が上がり、情報共有にも役立っています。
顧問弁護士サービス「かなめねっと」について詳しくは、以下のサービスページをご覧ください。
また以下の記事、動画でも詳しく説明をしていますので、併せてご覧下さい。
▶︎参考:介護施設など介護業界に強い顧問弁護士の選び方や費用の目安などを解説
▶︎参考:【介護・保育事業の方、必見】チャットで弁護士と繋がろう!!介護保育事業の現場責任者がすぐに弁護士に相談できる「かなめねっと」の紹介動画
弁護士法人かなめには、介護業界や労働問題の分野に精通した弁護士が所属しており、丁寧なアドバイスと適切なサポートを行うことで、介護事業所の皆様の問題解決までの負担等を軽減させることができます。現在労働審判手続きについてお悩みの事業所の方は、早い段階でお問い合わせ下さい。
8−3.弁護士費用
(1)顧問料
- 顧問料:月額8万円(消費税別)から
※職員の方の人数、事業所の数、業務量により顧問料の金額は要相談とさせて頂いております。詳しくは、以下のお問合せフォームまたはお電話からお問い合わせください。
また、顧問弁護士サービス以外に弁護士法人かなめの弁護士へのスポットの法律相談料は、以下の通りです。
(2)法律相談料
- 1時間3万3000円(税込み
※相談時間が1時間に満たない場合でも、1時間分の相談料を頂きます。
※法律相談は、「1.弁護士法人かなめにご来所頂いてのご相談」、又は、「2.ZOOM面談によるご相談」に限らせて頂き、お電話でのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。
※介護事業所の経営者側からのご相談に限らせて頂き、他業種の企業様、職員等一般の方か らのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。
9.まとめ
この記事では、労働審判対応を弁護士に相談するメリットや、弁護士に依頼した場合の費用について解説しました。
労働審判対応を弁護士に相談するメリットは以下の通りです。
- 法的な専門知識や経験に基づいて適切に対応ができる。
- 労働審判を有利に進めるための戦略を立てることができる。
- 事業所の精神的な負担を軽減することができる。
- 労働審判から訴訟へ移行した場合にも一貫して対応できる。
- 事業所にとって最善の解決をするためのサポートが得られる。
また、事業所側の労働審判対応の弁護士費用は、請求される金額を基準に計算されることが一般的です。労働審判対応において、特に事業主側の場合は申立書が届いてから答弁書を提出するまでに期限があり、しかもかなり短期間であるため、非常に難しい対応が求められます。
事業所の負担を軽減し、最善の解決をするためにも、労働審判対応は速やかに弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人かなめでは、数々の労働審判に関するご相談に対応してきた実績があり、迅速かつ的確な労働審判対応により、多くの事業所の方からの信頼を得ています。労働審判の対応でお困りの介護事業者の皆さんは、弁護士法人かなめまでご相談下さい。
10.【関連情報】労働審判に関するその他のお役立ち情報
今回の記事では、「労働審判対応を弁護士に相談するメリットとは?費用や相場について」を詳しく解説してきましたが、この記事でご紹介していない労働審判に関するお役立ち情報も以下でご紹介しておきますので、あわせてご参照ください。
・労働審判での解決は会社側に不利ではない!その理由や対応のポイントを弁護士が解説
・記事更新日:2026年2月5日
「弁護士法人かなめ」のお問い合わせ方法
介護事故、行政対応、労務問題 etc....介護現場で起こる様々なトラブルや悩みについて、専門の弁護士チームへの法律相談は、下記から気軽にお問い合わせください。
「受付時間 午前9:00~午後5:00(土日祝除く)」内にお電話頂くか、メールフォーム(24時間受付中)よりお問合せ下さい。

介護事業所に特化した法務サービス「かなめねっと」のご案内

弁護士法人かなめではトラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入しています。他にはない対応力で依頼者様にご好評いただいています。
「かなめねっと」では、弁護士と介護事業所の関係者様、具体的には、経営者の方だけでなく、現場の責任者の方を含めたチャットグループを作り、日々現場で発生する悩み事をいつでもご相談いただける体制を構築しています。
法律家の視点から利用者様とのトラブルをはじめ、事業所で発生する様々なトラブルなどに対応します。 現場から直接、弁護士に相談できることで、社内調整や伝言ゲームが不要になり、業務効率がアップします!
介護業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー開催情報
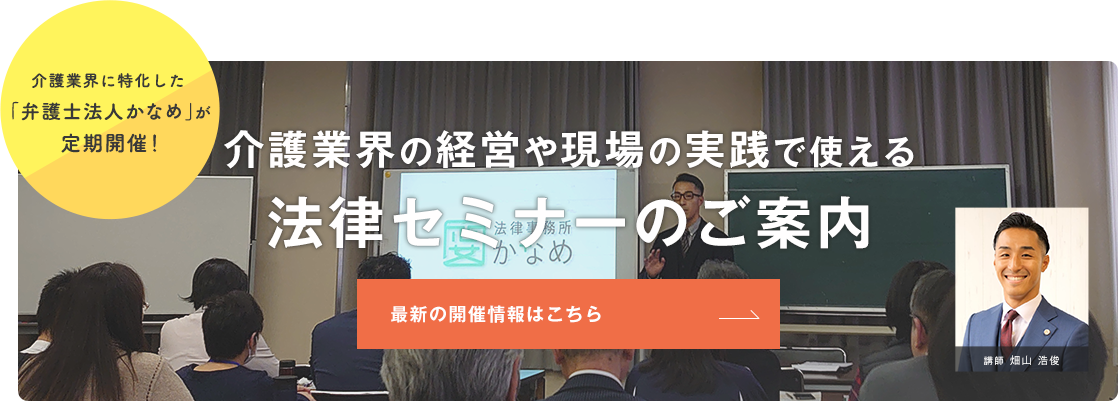
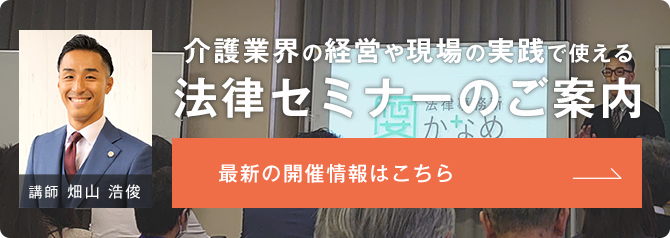
弁護士法人かなめが運営する「かなめねっと」では、日々サポートをさせて頂いている介護事業者様から多様かつ豊富な相談が寄せられています。弁護士法人かなめでは、ここで培った経験とノウハウをもとに、「介護業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー」を開催しています。セミナーの講師は、「かなめ介護研究所」の記事の著者で「介護業界に特化した弁護士」の畑山が担当。
介護施設の経営や現場の実戦で活用できるテーマ(「労働問題・労務管理」「クレーム対応」「債権回収」「利用者との契約関連」「介護事故対応」「感染症対応」「行政対応関連」など)を中心としたセミナーです。
弁護士法人かなめでは、「介護業界に特化した弁護士」の集団として、介護業界に関するトラブルの解決を介護事業者様の立場から全力で取り組んで参りました。法律セミナーでは、実際に介護業界に特化した弁護士にしか話せない、経営や現場で役立つ「生の情報」をお届けしますので、是非、最新のセミナー開催情報をチェックしていただき、お気軽にご参加ください。
介護特化型弁護士による研修講師サービスのご案内
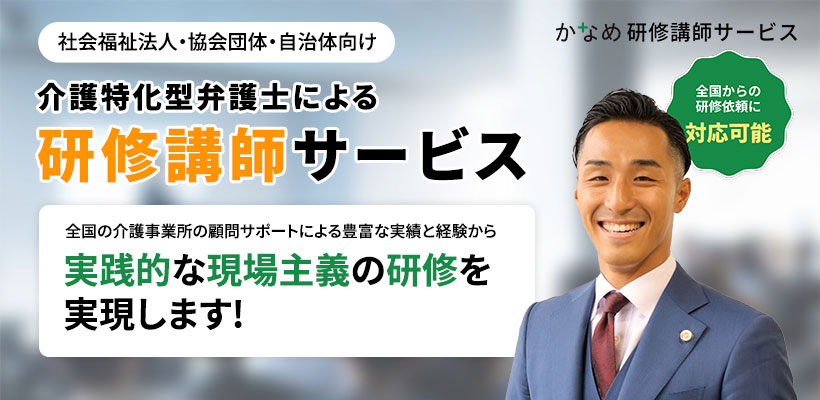
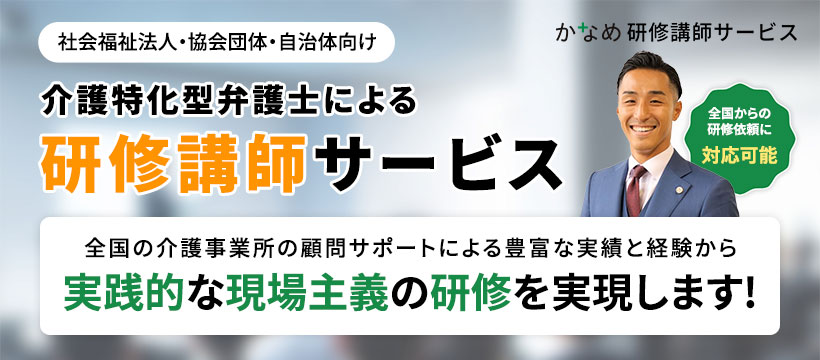
弁護士法人かなめが運営している社会福祉法人・協会団体・自治体向けの介護特化型弁護士による研修講師サービス「かなめ研修講師サービス」です。顧問弁護士として、全国の介護事業所の顧問サポートによる豊富な実績と経験から実践的な現場主義の研修を実現します。
社会福祉法人の研修担当者様へは、「職員の指導、教育によるスキルアップ」「職員の悩みや職場の問題点の洗い出し」「コンプライアンスを強化したい」「組織内での意識の共有」などの目的として、協会団体・自治体の研修担当者様へは、「介護業界のコンプライアンス教育の実施」「介護業界のトレンド、最新事例など知識の共有をしたい」「各団体の所属法人に対して高品質な研修サービスを提供したい」などの目的として最適なサービスです。
主な研修テーマは、「カスタマーハラスメント研修」「各種ハラスメント研修」「高齢者虐待に関する研修」「BCP(事業継続計画)研修」「介護事故に関する研修」「運営指導(実地指導)に関する研修」「各種ヒヤリハット研修」「メンタルヘルスに関する研修」をはじめ、「課題に応じたオリジナル研修」まで、介護事業所が直面する様々な企業法務の問題についてのテーマに対応しております。会場またはオンラインでの研修にご対応しており、全国の社会福祉法人様をはじめ、協会団体・自治体様からご依頼いただいております。
現在、研修講師をお探しのの介護事業者様や協会団体・自治体様は、「かなめ研修講師サービス」のWebサイトを是非ご覧ください。